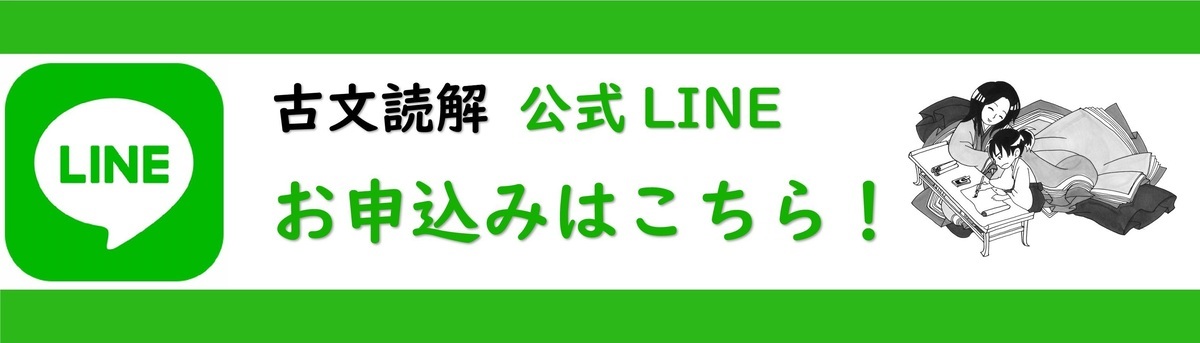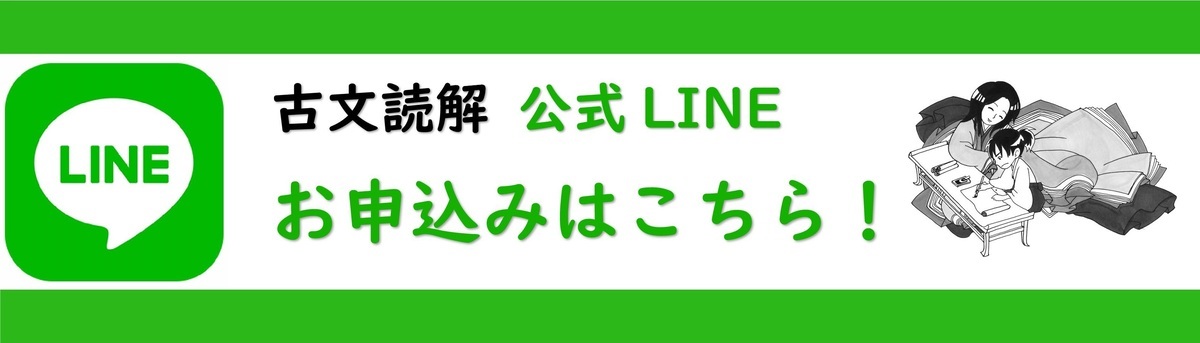「解いた問題数」よりも【解ける問題数】を増やす塾。
(草津校)
077-574-8190
(南草津校)
077-566-2804
古文読解 基礎編
- 授業回数:全部で9回
- 費用:3,300円×9回=29,700円(税込)→27,500円(税込)
- テキスト:PDFファイルを配布
- お支払方法:銀行振込(一括)
- お申込方法:下記の公式LINEにご登録。詳細をご案内します。
古文読解 基礎編の内容・レベル
古文読解 基礎編 第1回
| 出典 | 古今著聞集 | レベル | ★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
今回の問題では、「会話の文か地の文か」を判断する練習をします。会話文とは、登場人物の言葉であり、地の文とは筆者の言葉で、ストーリーの説明などに使われる言葉です。古文には、もともとカギカッコはついておらず、すべて地の文として書かれています。それを、少しでも分かりやすくするために、出題者が「 」をつけてくれている文もありますが、残念ながらすべてに「 」がついているわけではありません。入試問題の中には全く「 」のない文章が出題されることもあります。 そこで、自分自身で「 」をつけられる練習を積むことで、会話文と地の文を明確に分けて読み進めていくと、ビックリするくらい話の内容がアタマに入ってきます。また、会話文なら「誰から誰へのセリフなのか」を押さえながら読むと、さらにクリアに内容が理解できるので、「問題を解くことなんて大したことないな」と実感できます。 | |||
古文読解 基礎編 第2回
| 出典 | 枕草子175段 | レベル | ★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
今回の文章は短いですが、「単語や文法を勉強したけれど、文の意味がとれない!」とよく言われる文章です。せっかく古文単語を覚えて、文法も覚えているのに、古文のストーリーがつかめないと高得点は望めません。ここでは、敬語もたくさん出てきますが、敬語を活用して文の意味をつかむ「最初の練習」としてはちょうどいい問題です。敬語は、文法の中で習う人も多いと思いますが、文章の中での使い方を明確に学んでいる人は非常に少ないんです。 | |||
古文読解 基礎編 第3回
| 出典 | 徒然草128段 | レベル | ★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
今回の文章には、敬語やカギカッコ、指示語の内容を押さえる、といった基本事項がたくさん出てきます。ただ、ここでのメインは、「+-を使った文脈のとらえ方」です。模試や受験本番では、どれだけたくさん古文単語を覚えていても「意味を知らない古文単語」が必ず出てきます。そこで、手が止まり、アタマが止まってしまうとテスト結果もおぼつきません。 本番で知らない単語が出てきても、前後の文脈から+-が判断できれば、たとえ現代語訳できなくても、問題は解けます!点数が取れます!「現代語訳しないと!」という呪縛から抜けましょう!古文読解のキモは、「主語・目的語を補って、大意をつかむ」ことです。訳せない部分は気にせずにいられるようになると、テスト本番でも冷静に読み進め、問題に集中できるので、今回の問題は「大意をつかむ第一歩」にして下さい。 | |||
古文読解 基礎編 第4回
| 出典 | 十訓抄 | レベル | ★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
今回の文章は、おそらく最初に読んだときに「よくわからない」「話が途中でわからなくなった」「結局、どうなったの??」という人が続出する文章です。だからこそ、今まで培ってきた「主語と目的語を補ってストーリーをつかむ」という実力が試されるいい問題です。 | |||
古文読解 基礎編 第5回
| 出典 | 徒然草184段 | レベル | ★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
今回の文章では、古文読解の一番大事なPOINTである「主語と目的語を補って読む」ということを再確認できる設問になっています。もちろん、実際の模試や入試本番では、そういった設問がなくても主語・目的語を補って読むことが一番の高得点への近道です。 また、練習・慣れが必要なのが「指示語の内容」を押さえること!!基本的な考え方は現代文と同じで「直前を探す」ことには変わりありません。それが古文になると迷子になりやすいので、「指示語のせいで、ストーリーがつかめなくなる」のを防ぐためにも、指示語の内容のつかみ方をマスターしていきましょう。指示語だけでなく、文脈の中の対応(同義:=、対義:⇔、因果:⇒など)を押さえていくと、知らない単語が出てきても恐れることなく、話をたどっていけます。 そして、最後は、しっかりと本文が読めているかどうかを試す「文章の主題」!! 今回は、一通り習った基本事項が身についているかを試す格好の問題になっています | |||
古文読解 基礎編 第6回
| 出典 | 宇治拾遺物語 | レベル | ★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
今回の問題のメインテーマは、『多義語の判定』です。古文単語は一通り覚えた、という生徒さんに多いのが「意味がたくさんある単語の場合、この文ではどの意味になるかわからない」という質問です。古文単語帳では、そこまで教えてくれませんから、目の前の文における意味を「その前後の部分」からどのように決めていくのか、というプロセスをしっかり聞いて下さい。 また、今回も指示語がバンバン出てきており、設問でも「指示語の内容を補って現代語訳」する問題も出題されているので、指示語の内容をつかむ練習にはもってこいです。 最後の問題は、この授業では珍しく助動詞の意味と活用形を問う文法問題なので、読解の中で助動詞の意味をつかんでいけるように練習していきましょう! | |||
古文読解 基礎編 第7回
| 出典 | 古今著聞集 | レベル | ★★☆☆☆ |
|---|---|---|---|
今回は基礎編で初めて「和歌」が出てきます。和歌を苦手とする生徒は多いので、この問題では和歌の読み解き方の基本を解説します。和歌は和歌単独で考えるのではなく、本文と和歌との対応を考えることでググっと和歌の内容がわかりやすくなります。和歌に使われる技法(掛詞や枕詞など)に惑わされて「わかりにくい・・・」と思うのは、出題者の思うツボです!和歌は登場人物の心情を詠んでいるだけなので、実はそんなに難しくありません。 和歌を読み解くためには、まずは和歌以外の「地の文」で「主語・目的語を補ってストーリーをつかむ」ことが必要不可欠です。だから、今までの第1回~第6回で、古文読解のコツをつかんで練習してきた土台の上に、今回の「和歌の読解」を積み重ねて下さいね。受講後は「和歌なんて恐れるに足らず!」と思えるようになるハズです。 | |||
古文読解 基礎編 第8回
| 出典 | 徒然草104段 | レベル | ★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
今回の文章は、「主語・目的語」があまりありません(笑)単語と文法だけでは、品詞分解ができても、話の内容はわからないままで終わることが多い文章です。 主語を補うことは、他の参考書などでも言われていますが、目的語(~を・~に)を補うことはあまり教えられません。用言(主に動詞)を見たら、「誰が」「どこで」「何を」しているのかを1つずつ把握することが、ゆくゆくはテスト本番で「正確」かつ「時間内」に解くことにつながります。今は、時間がかかってもいいので「正確さ」を身に付けましょう!難しい文章でも、易しい文章でも「基本技術」は変わりありません。難しい文章でも、「いつもと同じ方法」で読み進めていけるようには、反復練習がカギです! また、本文の中にある「対比」に気付けるかどうかも設問になっているので、「基礎編 第5回」で学習した内容を生かして設問に取り組んで下さい! | |||
古文読解 基礎編 第9回
| 出典 | 徒然草10段 | レベル | ★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
基礎編の最後、第9回です。基礎編の最後にふさわしく、今までのPOINTが全部入っています。主語・目的語を補う、カギカッコをつける、指示語の内容をとらえる、敬語の活用といった「基本の4POINT」はもちろん、+-で文脈をつかむ、できるだけ漢字に直して意味をつかむ、など盛りだくさん! 設問も、現代語訳だけじゃなく、空欄補充、文法の識別など、文法問題と読解問題の両方がしっかり入っているので、「時間を計ってテスト形式」でTryすることをオススメします。 最後の問題は、文章のテーマ・主題を答える記述問題になっているので、基礎編で培った実力がどれだけ通用するのかを試せる良問です。 しっかり根拠を持って解けた人は自信を持って次の演習編に進みましょう。解けなかった・・・(>_<)という人は、まだ「定着」が甘い可能性があるので、基礎編を何度も復習して、「人に説明できるレベル」までやり直してから、次に進んで下さい! | |||
お申込みいただくと、全9回を受講できます。
- 費用:3,300円×9回=29,700円(税込)→27,500円(税込)
- テキスト:PDFファイルを配布
- お支払方法:銀行振込(一括)
- お申込方法:下記の公式LINEにご登録。詳細をご案内します。